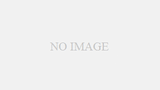働かない「おじさん」とは?
近年の定年制の延長に伴い、雇用期間が長期化した中で、求められる役割と賃金に見合わない「中高年男性の働きぶり」に対して呼称されていますが、明確に定義づけられてはいません。全く仕事をしないという人は現在の企業でいないと思います。主に外部環境の変化に合わせて、企業方針などが変わる中、変化に対応できず、成果を出せていない人や「役職定年」後に年功制の為、給与は一定の水準のまま、仕事内容のと本人の成果や役割認識がズレているような状態に使われているケースが多いです。
働かせてない企業
ひと昔、前までは定年は60歳でしたが、70歳努力義務になり、企業も予定外に長期雇用を強いられています。日本企業を支えてきた「新卒一括採用」「年功制」「企業別労働組合」の3種の神器が長期雇用含めて合わなくなって来ている企業が増えているのでは無いでしょうか?「人口ピラミット」で若い人が多く、年配者が少ない構成で「年功制」は「役割や給与」も合わせて機能していた所もありますが、「団塊ジュニア」50代が多く、20代が少ない、30代は転職で不在している様な企業を良く見かけるようになりました。このような企業では成長した30代がポストが無いため離職する事や組織が停滞することを懸念して「役職定年」「早期退職制度」など「人事制度」の変更を行っている企業がありますが、バブル崩壊から平成大不況期に入社し会社から言われるように働いてきた人たちが、今「働かないおじさん」として企業からも見放されようとしています。日本の雇用では解雇は難しいケースが多い為、働きにくい環境(無理な配転)を提供して「退職勧奨」を実質進めている。今までの「居場所」を奪い「配転」して強みを発揮できていない状況の方も多いのではないでしょうか?また、頑張ろうとしても「業務内容」を理解していない中、年下から教えてもらえない(教えを請わない)人もいるため、職場の中でも浮いた存在となり「自己効力感」も下がっている状態に企業や人事は見て見ぬふりをしているケースもあります。このような状況は「おじさん本人」だけでなく、「職場の雰囲気や生産性」も低下させてしまい、誰にとってもいい結果を招かない状態になります。
働きたいおじさん
団塊ジュニア世代のおじさん達は企業に対してのロイヤリティが高く、勤労意欲が高い人が多いとある調査でもでています。(著者が在籍する自社のサーベイでも)ただ、周辺の環境変化に適応できていないケースが多い為、人事が間に入り「期待」を「具体的」に伝える事で戦力として貢献してくれます。「自分の居場所」がここにある。「周りの為になっている」と感じる事が出来る環境を整える必要が企業には求められてきます。(放置期間が長いと本当に何もできない人になるので、早い段階からのキャリア意識を持たせておく必要があります)
年齢を重ねても活躍できるおじさん
みなさんの周りにも活躍できているおじさんはいませんか?(この場合のおじさんは管理職や経営者は除く)①仕事そのものが好きで常に感謝をしながら働いている方(今までの経験を活かし創意工夫も行う)②仕事以外にやりたい事が明確にあり、その為に仕事をしている方③自己成長意欲が高く常に新しい事に取り組んでいる方。私の周りで活躍されている上記方々は会社からも重宝され、定年退職後も再雇用を取り付け70歳を過ぎても変わらず働かれています。若手の社員よりもパフォーマンスが高く、管理職との関係性も非常に良好です。上記のおじさん方は「自己理解」が出来ていて、且つ「周囲からの期待も理解」できている状態です。
煙たがられるおじさん
本人に悪気はないのですが、周囲から煙たがられるおじさんの例をいくつか紹介します。①経験したことを話して後輩に仕事をさせないおじさん。後輩が始めようとしている仕事に対して「過去にやって上手く行かなかったから」と頭ごなしに否定して、相手の話を聞かずに自分の話を延々としてしまう方。本人からすると「アドバイス」をしているつもりですが、周囲のやる気をそいでしまっています。②過去に成功体験があり、やり方を変更しないおじさん。これはおじさんに限りませんが、時代(顧客の変化)に合わせたビジネスモデルが必要と頭では分かっているものの、自身の成功体験に引きずられ、考え方・やり方を変えられない方は次第に仕事も減ってくる可能性があります。③些細なことをしないおじさん。今までの役職があった方や〇〇は若い人がすると思い込んでしまっている(昔はそれで良かった。先輩がそうだった)例えば社内に掛かって来た電話を取らない。来訪者の対応をしない。など。そもそも「俺がする必要あるか?」とまでは思い込んでいなくても「周囲の方がやってくれる」と思い込んでしまい。何かにつけて動きが少なくなってしまう方。④給与が下がったと周囲に行ってその分働かないと言っているおじさん。(下がった給与が外部の市場と比べても、能力や成果よりも多く貰っているとしても、その事に気づかず「不満ばかり」を周りに話しているおじさん。⑤突然「キレる。怒鳴る」おじさん。年齢とともに前頭葉の機能低下で感情が抑えきれなくなり、怒りの感情を終えられなくなると言われています(個人差はあるそうですが)最近、私の周りでは「50歳過ぎたので我慢する必要はないからね。」などの会話をされている方々が男女問わず見かける様になりました。いい意味で吹っ切れて本音で話が出来る様になるケースもあれば、「自分勝手、わがまま」になるケースもあります。特に役職が高い人は注意が必要(役職がある方のわがままと「仕事」として受け止めているケースがあるため、本人が気づかない)役職が無いケースでも若者に対して突然怒鳴りつけている人を見かけます。普段から不満を感じやすい体質になっているケースもあるため、話ができる仲間や環境が必要になります。
好かれるおじさん
一方で仕事はそこそこでも「好かれるおじさん」もいます。私の会社では①相手の話を引き出すのが上手い(ついつい自分の知見を話したくなると思いますが・・)人は話を聞いてくれる人に好意をいだきます。(自分自身の存在を認識されていると感じる為)②執着心が無い(弱い)。年齢による変化を受け止める事で、次の自分の進化している方は「今までの自分を手放す」事が出来ています。今までの様に出来ない環境に対して必死に抗っても「社内での地位や役職」が戻ってくるわけではありません。環境変化が激しい時代だからこそ、切り替え上手になる事が求められてきます。③自分に不向きな事を知っている。自分に向いていない事をしっかり周りのサポートを受けながら取り組める方。自らの出来る事で返していく行動をとるので、依存のみではなく、「相互依存」という関係で働かれている方は好感度が高く継続した仕事をされています。
いつか働かないおじさんにならない為に
40代で今バリバリ仕事をされている方で現在の職場で定年まで働こうと考えている方へ①今後のキャリアプランをいくつか考える機会をお薦めします。順調に昇進ルートを進んでいる方は特にそのルートが無くなった時や役割を終えたときに「自分自身の価値観や出来る事の整理が出来ていないままの状態で次に進んでしまうと働かないではなく、働けないおじさんになる可能性があります。人生100年時代を迎えて、いつまで働くのか?も含めて自らの人生設計を見直してはいかがでしょうか?②自らの市場価値を知る。高める。定年まで今の会社で働こうと考えている方は今の会社に不満が少ないと思います。転職経験の無い方の場合、自らの履歴書を改めて作成する事は今まで無かったと思います。今まで何をやってきて、今「何が出来るか?」を改めて整理する中で、自らの価値観を整理できますし、価値観に基づいた仕事と報酬が現在と比べて高いか低いか?を知って置くことも大切です。知ってほしい事は、世の中の求められる仕事基準(今の自分の仕事と比べて高いか?低いか?)報酬レンジ(世の中の仕事に対しての報酬イメージを掴む)もし、世の中の仕事基準が高く、報酬は今の職場が高いとした場合に「給与泥棒」になっているかもしれません。改めて「能力開発」を自ら行う必要があります。③師匠を見つける。出来れば社外で活躍している60歳以上の方と知り合いになり、相談できる関係性を築いておくと今後の人生において判断しやすい状態になります。社内の人は「同じ価値観」の方が多く、良いも悪いも現状から変化しようという人に対して中立な立場から話が出来ない場合も多い為、出来れば2人以上は「キャリア自律している方(起業もしくは個人事業)を師匠に持つと定年後の人生プランも描きやすくなります。
今、働けていないおじさんへ(頑張りたい人)
今の会社で「やりがい」を感じずに仕事をしている?方で何とか今の状況を抜け出したいと考えているおじさん。あなたは非常にまじめな方だと思います。「誰かの役にたっているのか?」「何の為に働いているのか?」「成長しているのか?焦燥感」サラリーマンという安定した状態であるのに妙に将来不安が拭いきれない「もやもや」が付きまとう。そのような日々が続くと精神的にも良くありません。今の年齢になって改めて「何故、この会社で働くのか?」「何を実現するのか?」など自らに問いかけて整理していく必要があります。手放す事で新たなことが手に入ります。執着を手放し、あなたらしく生きるために「何を始めるか?」を決めていきましょう。
まとめ
社会現象としても取り扱われる「はたらかないおじさん」は企業や環境が作り出してしまうケースが多く、緊張感が無い、雇用関係が長期間続けば、誰しも「働かないおじさん」になってしまいます。会社におんぶにだっこという形は会社・人事は望んでいないと思います。年を重ねても「健全な競争社会」の中で「健康にイキイキ」と働くミドル/シニアが見えるからこそ、20代の若者も未来に期待が出来るのでは無いでしょうか?その為に企業側は「ミドル・シニアも活躍できる環境提供」個人は「自己研鑽やアップデート」を行い持続的に活躍していきたいですね。