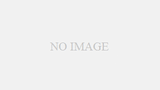従業員サーベイを検討している方、導入していて活用に悩んでいる方に向けて、解説します。
従業員満足度調査とは?
従業員が働く上で、業務内容、処遇(評価)、福利厚生、人間関係、職場環境などを定性的な質問に対して数字による段階評価を行い、総合的に数値化して計測することです。海外では歴史があり、フレデリック・ハーズバーグの二要因理論(動機付け要因・衛生要因)やアブラハム・マズローの欲求階層説(5段階、6段階に人間の欲求を分けたもの)があり、人材の定着や生産性向上、顧客満足につながるとされ、研究がされてきました。日本でも2000年前後から従業員満足度調査が行われ始めたそうですが、重視されるようになってきたのは近年の「人的資本経営」への取り組みとして上場企業を中心に開示が求められるようになってからだと感じます。それまでは、2017年に米国のギャラップ社が世界各国における従業員のエンゲージメント調査が行われ、139か国中132位と低く、話題になったことで、その後「エンゲージメント(従業員満足)が仕事の生産性に繋がるという話が使われるようになってきたと言われています。
顧客満足と従業員満足はどちらが先か?
鶏が先か卵が先か?のような話ですが、利益を出す為にお金を使ってくれるのは「お客様」です。お客様に対して価値提案するのが「従業員」になります。利益が生まれることによって、会社は社員に還元していく事ができますし、新たな投資や採用など行うこともできます。つまり、最終目的は企業価値が上がることで三方良し(お客様・従業員・会社)の状態になります。そこに行きつくためのプロセスとして「従業員満足」が必要になります。近年のビジネスモデルはコモディティ化が進んだ状態では「差別化」される要素が少なく、「価格競争」へ進む事は企業にとっても、従業員にとっても利益低下を招く要素になる為、良いことではありません。そこで、従業員の満足度が高い状態なら、自社の優位性を築くことも出来ます。(従業員そのものが差別化になる事ができる為)ただし、気を付けないといけないのは、「人は生もの、常に浮き沈みがあります。」今日はやる気に満ち溢れていても、明日も同じ状態とは限りません。また、環境の良さにもすぐに慣れてしまいます。従業員満足度を上げる事は大切ですが、何を大切にしている会社なのかを理解浸透しながら、「行動変容」に繋げていくことも平行して必要になります。
従業員満足度調査の目的の明確化
従業員満足度調査をする際に気を付けるポイントは「取り合えず現在のスコアを図ってみよう!」という興味本位で始めることです。目的が分からない「アンケート」に回答する社員は「苦痛」を感じる事になります。結果出てきた調査結果に対して、「経営層」「幹部層」が面白くない結果が出ると、受け止める事よりもそもそも調査に対して苦情を言って来たりします。360°評価を経営層や幹部層にしたときに「怒ったり、犯人捜しをしたり」ネガティブに目を向けて返って関係が悪くなることもあります。大手の顧客満足度調査になると、「〇〇部門no.1」のような、広報目的を狙う会社さんもいらっしゃると思います。自分の会社を良く見せたい経営者が広報目的に飛びつき、結果スコアが伴わず、目的と違う所で苦戦する事もあります。(スコアを取って何もしなければ、返って従業員からの不信を招き調査する前よりも関係性が悪くなることも・・・)対外的な事を意識して「社員を操作」しようとすると「忖度」か「反発」が出て結果、現状出ているスコアに対して実態が伴わないこともあります。スコア高いが「離職が多い」「業績が低い」など、それでもリクルートを強化する為に導入して成功している会社もあります。結局「導入の目的」を明確化する事が一番かと思います。人事から提案する場合は経営者と良くすり合わせしていないと、スコア結果から経営者に動いてもらう所まで必要になりますので、どの様な「組織を目指している」から現状をスコアリングしたいという事が「経営戦略」と重なって置く必要があります。また、「従業員」に対しても「何の為に調査するのか?」を落とし込んでないと、「めんどくさいので適当につけておこう」という結果にもなります。導入する際は「経営者、幹部、人事、現場社員」が目的を理解して進めていく事で始めて調査の必要性が出てきます。
調査で見えるもの、見えないもの
調査していく中で見えてくるものと、見えないものがあります。従業員満足度調査はあくまでも「マス」で情報をとらえるもの(組織を1つの人格としてみるイメージ)になるので、平均値が映し出されます。会社に対してロイヤリティがmaxの人とminimumの人がスコアを付ければ結論は平均的なスコアです。分母の数が多ければカバーできるものもありますが、あくまでの参考として捉えておく必要があります。
継続の必要性
一回取り出したら、最低2年は続けて欲しいと思います。組織開発をするうえで、すぐに結果が出てくるものではない(すぐに改善したスコアが出た場合は次に悪い方に変化する可能性あります)年に何回とるかにもよりますが、 2年ぐらいの経過を見ている方が対策に対しての効果も見ていく事が出来ます。また、スコアの悪いところに目が行きその部分の改善に捉われてしまい、「導入時の目的」を見失う可能性もあるため、「目指したい組織」に向かっての進捗(変化)を最優先にしてアクションしていきましょう。
まとめ
従業員には「イキイキ」と仕事をして欲しいと思う経営者は従業員満足度調査を活用することで、更にいい会社づくりを目指していけると思います。ただ、目的を見失い「スコア」の上がり下がりに一喜一憂してもしかたありません。中長期的な目線で「従業員満足度」と「会社の利益」がリンクしていけば「働きがいのある会社」として内外から認められる会社になっていきます。組織づくりは一朝一夕で作り上げる事はできませんので、胆力をもって臨んでください。