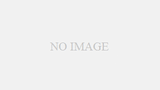管理職の役割について解説します。
管理職とは?
みなさんは、「管理職」と聞くとどの様なイメージを持たれていますか?課長、部長など「役職」を想像されますか?部下の業務を管理する人、業績を出すために各個人を束ねる人、部下を育成する人など「役割」を想像されますか?又は、大変そう、なりたくない、社畜など「ネガティブ」な想像をされますか?皆さんにとってそれぞれイメージを持たれていると思いますが、改めて、管理職を調べてみると、企業で部下を管理し、組織の運営を担当する「職位」主に課長や部長の「役職」を指しています。管理職の「役職」定義は企業により様々です。係長以上を管理職としている会社もあれば、呼称で課長はいていも課は存在せず、決裁権も一般社員と同じ場合もあります。会社の都合に合わせて、管理職という「立場」が存在しています。
管理監督者との違い
労働基準法上の管理監督者は「労働条件の決定」や「労務管理」に権限を持つ労働者で「監督もしくは管理の地位にある者」と定義されています。「管理職」は法律上定義づけられていません。「役職名」のみではなく、実態として「責任と権限」があるかで判断されます。
管理職の役割は?
管理職の求められる責任を大きく3つに分けると「業績責任」「部下育成責任」「上司へ提案責任」があると私は考えています。1つ目の「業績責任」が最も会社からも求められると思いますが、自身の所属部署に任された目標をいかに達成できるか?という事が求められると思います。もともとプレイヤーとして業績を出した方が管理職になるケースが多いため、管理職自身も得意分野であればここに大部分の力を割かれる方が多いと思います。業績責任はプレイイングマネージャーをすることで業績を出すこともできますので、仕事をしている気持ちにもなりやすいです。しかし、自らの能力の限界を超える目標が設定されると一人の力では到底追いつけないようになります。また、あなたの右腕左腕の存在が出来れば、さらに高い成果を上げる事ができますので、2つ目の「部下育成責任」は重要になってきます。「部下が成長していく姿」を間近で見ていく事ができるのは管理職としての楽しみの一つかもしれません。しかし、会社は常に目の前の数字(業績)を求めていますので、今日、明日で部下が成長するわけではありませんので、中期的な視点で見ていく必要があります。3つ目は「上司へ提案責任」です。上意下達という言葉がありますが、ビジネスモデルの成功している間はいかに早く現場で徹底させる。という流れがいいかと思いますが、近年は成功モデルの時間軸が短くなっています。今までの成功パターンの影響が大きいほど、変化できない組織になっていく場合が多くあると感じています。そこで重要になってくるのが、現場に近い「管理職」の存在です。部下達の些細な会話から「顧客」がどの様な変化をしているか?推察しながら、情報を収集し現場で改善出来ないような大きな取り組みに対して速やかに上層部へ提案し、改善をしていく必要があります。ボトムアップと言われるものになりますが、「現場」の改善は部下が気づて出来るものもあれば、部下自身が気づかないものもあります。その時に「管理職」が俯瞰した状態で現場の状況と会社の方針にズレが無いのかを確認していく必要があります。そのスピードが遅くなればなるほど、経営の判断も遅れてしまいます。「上司への提案」は「管理職」にとって非常に大切な仕事になります。
理想はマネジメントしないこと!?
みなさんもご存じのピーター・ドラッカーは自律的な組織においては、「管理職=ミドルマネジメント」は不要になる可能性がある。と話をしています。成果を上げる為に組織の目標やミッションを理解した集団が自律的に話し合いながらプロジェクトを進めていく事ができれば、管理する人=役割として不要になる可能性はあります。一人ひとりが専門性を持ち、コミュニケーションを取りながら優先順位をつけて仕事を進めていく事が出来れば確かに成果が上がるイメージがつきます。しかし、実態は決裁権や特に人材育成の面から組織構成が20代の未経験者と40,50代の管理職という「間の世代」がいない組織をよく見かけます。(どこにこの世代が行ってしまったのか?と感じるところもありますが)この様な状況下においてはシュチュエーションリーダーシップが必要となり、現代の若者に興味関心を抱かせながら、仕事を教えて、かつ成果を上げていく高度なマネジメントスキルを現在は必要とされています。(就職氷河期に入社した私からすると全く持って違う時代になったと日々感じる次第です。)
広がる管理職の役割
バブル時代に比べて管理職が抱える業務の量及び部下の人数割合は増加している会社が多く管理職が不足して、兼任(複数の組織を管理している)している方をよく見かけます。近年は管理職の業務量の多さを見て、「なりたくない」という若者も増えてきています。管理職1人に対してマネジメントする人員数が増えたり、業務内容が異なる部下をマネジメントするなど、役割が多岐に渡っています。また、近年のコンプライアンスを意識の高まりなどから、経営者も管理職に対しての研修を行い、部下のマネジメントに対してなど細やかな気配りも求められます。とにかく色々な事をする必要がある。と感じています。一昔前、tvドラマで見ていた、サラリーマンとして上がりのポジション(部長?)として何もしない?(誤解)からは大きく時代が変わったと認識せざるを得ないでしょう。特に近年は「人事制度」を改訂している企業が多く、年功制→管理職のジョブ型(期待役割制度)へ移行している企業が増えています。温情的に長く会社にいるからポストがもらえるのではなく、期待される役割が発揮してもらう為に、要件定義された職務をこなしていく必要があります。
一度はやる価値がある「管理職」
世間ではやりたくない人が増えているからこそ、市場価値として「マネジメント経験人員数」などが評価されるようになってきています。管理職を長期間していくことはしんどい部分はありますが、自らの価値を上げるためにマネジメント経験を積むという考えもあります。
まとめ
時代の変化に合わせて、管理職に求められる事も変化しています。しかし、変わらないものもあります。それは、「会社と現場を繋ぐ役目」です。フラット型組織、テール型組織、などなど様々な組織論が世の中に出ては来ていますが、一般的には組織に所属する人数が増えると、社長だけでは目が行き届かなくなり、社長本来の力を発揮することが出来なくなります。現場の社員も社長の決済を待っているだけで仕事が進まないなんてことになるかもしれません(過去にハンコを貰うために並んでいる風景を見たことがありますが)すべて現場で決済するにしても、責任がついてくる以上社員も不安が出てきます。社長も社員も安心して仕事が出来るためにも管理職が間に立つことで仕事を円滑に進める事が出来ます。ただし、注意しないといけないのは、階層が多い場合や、同じ組織内に同じ肩書の方が2人以上いる場合など、その階層や役職の「役割」があいまいである場合に、コミュニケーションコストが発生して、社長の指示が現場に全然伝わらないという状況もあります。適度な人員数に合わせた管理職の「階層」「役職」などを設定することで、コミュニケーションと生産性のバランスを取れた組織づくりを目指してください。また、管理職の楽しさ(人材育成やチームで成果を上げる感覚や上司を動かして改善や改革を進める等など)も是非伝わるような会社づくりを目指していきましょう。