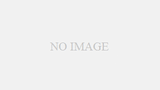生産性向上を掲げても、失敗した事例を紹介します。
・業務改善や生産性向上の担当になっている方
・管理職の方
・人事制度を企画される方
・生産性が上がらずに悩んでいる経営者の方
の参考になれば幸いです。
失敗その1_経営者の発信のみで具体策が無い。
近年の市場の変化や社会の動向を「経営者」は常に頭の中にあり、会社を維持または発展させるためにどうすれば良いか日夜悩み考えていると思います。しかし、「従業員」は「経営者」ではないので、同じような目線に立つことは中々できません。また、会社が大きくなり、分業化されている仕事になると益々全体的な仕事や経営環境は見えなくなります。「何故。生産性を向上しないといけないのか?」が「自分事にまで出来ていない」と行動に繋がりません。「何が具体的な課題」となっているか?それに対しての「うち手」は何か?が必要になります。
また、「従業員にとってのメリット」が伝わると行動変容に繋がります。
「業務改善!生産性の向上!変革・改革が必要だ!」は従業員にとっては「やばいよ!やばいよ!」って「何がやばいの?」としか捉えられていない可能性があることを理解しておきましょう。
失敗その2_管理職に丸投げする場合
生産性の目標設定のみ経営で決めて、あとは宜しくのパターンになると、「管理職の能力任せ」になり取り組みや結果にもバラつきが出ます。管理職も新任からベテランまで経験値も異なりますし、ベテランの方が自身の成功体験に捉われて行動変容するまでに時間が掛かる場合もあります。
また、取り組み出来るための「リソース」を用意しておくことが必要になります。管理職の経営戦略への理解度を上げるために、個別に面談など行い、「どの様な取り組みで生産性を改善しようとしているか?」を確認しながら、「支援」することを決めて行きます。情報理解を高めて、モチベーションを高め、行動の具体化が無いと現場と衝突して失敗に終わるどころが、関係性が悪くなり、逆に生産性が低下する場合もあります。特に階層が多い場合は経営側に近い役職と現場に近い役職で衝突が生まれる場合もあります。経営戦略に合わせて「各部門の中で、どの様な事を改善していくために」前後工程の部門やコーポレート部門は「何をいつまでにするか」部門を超えた取り組みの調整役は最終誰が決定していくのか?など事前に取り決めしていく事で止まっている部門が見える化され、次の改善アクションを取りやすくなります。
失敗その3_現場の気持ちを理解していない場合
現場の従業員に合わせていたら、何も進まないから、トップダウンでどんどん変化させていくというやり方もあります。経営者の顔が見えて、従業員の満足度の高い組織なら、経営の意思に沿って行動してくれますが、今、目の前の仕事に「やりがい、誇り、こだわり」をもっている「従業員」に「変化しろ、やり方変えよう!」など日常的に飛びっかている言葉が何故か上滑りしていることがあり、従業員からの立場から見ると「また、言っているよ」という気持ちになって行動に移していない個人や組織が見受けられます。バックオフィス部門の仕事をDXで効率化しようとして仕事の担当者にヒアリングした結果、中々改善策が出てこないというケースもあります。従業員側からすると今までの慣れた仕事や愛着がある業務まで無くなることで、自分自身の存在価値を脅かされる事になっていると認識しているかもしれません。特にパート社員や契約社員の業務を軽く見てDX化しようしてもこの仕事が無くなった時に私はどうなるのか?の心理面のハードルを先にクリアさせて初めて改善策が生まれてきます(トップダウンで介入する方法もありますが)お客様や従業員から日々の業務の中で「感謝される」仕事をDX化する場合には「コミュニケーション機会を喪失」する事もあります。「お客様」や「従業員」の声を業務改善に活かす事で成果に繋がる事も多くあります。人件費削減を考えるのも大切ですが、「顧客の声」が直接聞けなくなった分どの様に補うかも合わせて検討していきましょう。
まとめ
生産性向上は企業にとって非常に大切な活動になっています。それだけに意気込みすぎて、失敗をくり返し従業員も愛想を尽かしているケースにならないように、経営者と従業員の双方向のコミュのケーション機会をつくり「意図」や「活動内容」への理解を深めていきましょう。また、一度発信すれば自走化するまでは、定期的にコミュニケーションをとり、何処につまずいているのかを見定めていく必要があります。目標においても「現実的な目標設定」を置き、「少し頑張れば出来る」と思ってもらうことが大切です。知識や技術が足りない場合には「トレーニング計画」を作成してアウトプットの場として取り組みすることで従業員のモチベーションや自己効力感を高めていく事ができます。
まずは、スモールステップで小さい改善を繰り返し行う事で成功体験を積んで行く事からスタートしてはいかがでしょうか?