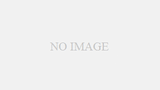創業者から代替わりする企業において、組織開発の参考をお届けします。
前回からのまとめ
カリスマ創業者から一族の2代目に交代したときの取り組みとして、
①2代目社長に夢を語ってもらう。(人となりを再確認)
②定期的に時間を取ってもらい話を聞く(社長になって価値観や見えてきたものがある為)
③周囲の協力体制の確認(古参の幹部や管理職)
④現場社員へのヒアリング(どの様に新社長を見ているか?何を期待しているか?)
2代目社長がやりたいことと幹部・管理職・現場社員とのGAPを把握することで、人事としての取り組むことが見えてきます。
発信できない環境に着目し改善
管理職や現場へのヒアリングを終えて、一番の課題に「発信者」が世代交代後も変わっていないことで、社員は今までと何も変わらない行動になっていました。(社長の思いは伝わっていない)課題を解決する為に行った事は以下の内容です。
①発信者(副社長)との面談(世代交代をしてもらう必要性を説得)
②週一で全社朝礼の実施(今、何を考えているかをダイレクトに社員に伝える)
③社史の作成(今までの会社を記録に残して、今後の新たな会社づくりのイメージを打ち出す)
④発信を社長に集める(社内発信情報や社外に向けた登壇を社長へ集めて、内外から注目を浴びる)
⑤コンピテンシーやブランドメッセージの変更(社内の評価基準や文化づくり、ステークホルダーとの関係性づくり)
発信情報を集める事で「一貫した内容」を届ける事ができ「会社が何を考えているかわからない」などの話は大きく改善されました。(従業員満足度調査より)
経営層のチームづくり
一方で経営幹部に関してはまとまってなく、お互いが自由に活動している形になっていました。役職はあれど、「経営チーム」としての役割は決まっていないという状況です。つまり、社長はいるけど、それを支えるというよりも、自分が主人公として会社を動かしたいと考える幹部層が複数いるような状態です。悪気無く、今まではそのような形であったとしても「カリスマ創業者」がいる前ではそこまでの存在感を出すことはできませんが、カリスマが去った後は「俺が俺が」という状態になっているという形です。実力や人望もある幹部が今まで創業者支えている事もあり、従業員や管理職に対しての信頼もある状態です。しかし、「船頭多くて船が船山に上ぼる」と使われる言葉があるように、方針に対しての戦略決定や実働について「あれやこれや」という意見が多くなると「決定するまでに時間がかかり」そこから「実行するまでに時間がかかる」という状態になっていました。新しく社長が中期経営計画を立ち上げ、幹部や全社員への説明会後の理解や実働まで時間が掛かりすぎ、1年6か月を費やしても、戦略・戦術が決定していないという状況になっていました。そこで、戦略の問題よりも「新しい経営チーム」として推進していく「役割認識不足」という事を「幹部陣」に知ってもらうために「経営チームづくり」に取り掛かりました。
経営チームの360°評価
経営チームづくりに対して、まずは現状「お互いの関係性やどの様な役割を期待されているか?」「どのように評価しあっているか」を可視化する為に。360°評価を実施しました。目的は「お互いが本音で話せる環境づくり」です。経営幹部の構成として、社長、常務、取締役、執行役員2名、本部長5名という構成です。この関係性を明らかにすること、部下からどの様にみられているか?の可視化から、各自の求められる「役割」について考えてもらうきっかけを作る為です。普段は評価する立場の人が評価される側に回るとその人が見えてきます。自己評価が高く周囲の評価が低い(過大評価タイプ)自分の評価を低くしてgapを少なくする人(傷つきたくないもくしは、自身が無いタイプ)評価を始める前に人が変わったように大人しくなる、優しさを出してくる人(結果を見て逆切れする、受け止めない人)など様々です。ここでは、社長と幹部との関係性作りをテーマにしていましたので、社長と幹部の1on1にファシリテーターを入れた3名で評価について面談していく流れをつくりました。実質1対1で話すことで、社長からの幹部への期待、幹部からの社長に対しての期待を話してもらい、関係性を作っていきます。ファシリテーターは会話の深堀りや表明的な会話にならないように話の流れによって介入していきます。ある程度、腹を割って話してくれる人もいました。これですぐに関係が出来るわけではありませんが、話を受けた内容をアクションとして各自が取り入れていく事で、信頼関係を構築していくのが目的です。(ここでやる人としない人の見極めも出来ます)
幹部層へ価値観研修の実施
本部長5名うち4名については40代前後の若手社員の抜擢人事を行っている為、引上げてもらったことで「yesマン化」してしまわないようにするために、「自分を作るための研修を実施しました」また立場上「判断」することが多くあります。そのたびに「ぶれ」がでると人の話に流されてしまいます。答えのないものを「判断」していきますので、当然間違った判断になることもありますが、各自の意見に一貫性を持たせていく事で「何に対してこだわりを持っている自覚を芽生えさせ、自他に公開していくことで回りもフォローしやすくなります。」また経験差のある「取締役層」と「対話」できる様にしていくために「自身の価値観づくり」を1年かけて行いました。実際しっかりと反対意見も含めた対話出来る様になるまで2年掛かりました。
幹部合宿の開催
本部長の価値観づくりに1年育成期間を設けて、対話できる育成を行いました。そのあとに経営チームでの幹部合宿を行い、個人間での対話から集団での役割認識を上げてもらうための合宿を行いました。ここでの目的は「各取締役に役割認識を持ってもらう事」「本部長から取締役に対して忖度なく意見を出してもらう事」これを目指して行いました。オープンな状況で各自の役割を可視化することで、各自が今何に注力することを求められているかを一致させていきます。時間はかかりましたが、一匹狼の集団から組織という形に変わり始める事が出来ました。(新社長就任から2年)定期的に合宿を開き互いの関係性や役割の可視化を行うことで関係性の継続が図れました。
本音で話せる環境づくりとして
サラリーマン経営者のチームでは「わが身が可愛い」「保身」に走ってしまう幹部もすくなからずいます。全体最適の俯瞰した視座で話ができず、自分に関わる事を中心に各論の議論に進む事があります。この様な状況になると中々議論も進まないケースがありますたので、「ファシリテーター」を置くことをお薦めします。司会とは別にファシリを置き、話を進展させたり、行き過ぎるときはブレーキを掛ける役になります。また、その状況を司会者が別で俯瞰して状況確認できることで参加者の心理的な変化に気づくことができ、後からファシリテーターとすり合わせができます。
②事前にセーフティーネットを共有しておく。社長に対して本心で話していく事に勇気がいりますので、この対話に対して本人を評価したりしないと「全員の前」で了解を得る事です。それでも疑い深い人もいますが、あえて口にする事で、後で何かあった時に全員の承認を取り付ける事につながります。
③経営幹部への期待として「今までの各自の功績を称賛しつつも、これが一つになった時にさらなる成長が期待される(期待感)を持たせます」本人たちの対話の重要感を持たせていく事で当たり障りのない会話で終わらせないような空気感を演出します。
④事前の良く発言するひとに根回ししておく。ファーストペンギンになってもらうことで、「こんな話をしても良いのか?そこまで突っ込んで良いのか?」と関係者に思ってもらうことで、それなら私も・・・という状況にもっていく。
まとめ
新しい社長が就任したときに、周辺の取締役や幹部社員が変わらずに一人「孤軍奮闘」して空回りするか?旧経営陣営がそのまま「社長をお飾り」にしてしまうか?会社により様々だと思いますが、あなたが、社長を支える立場の役割を担っているなら、「社長が出来ないこと」をやることがあなたの役割になります。一枚岩の「ワンチーム」にすることが理想ですが、実際は社長の「この指とまれ!」になっていない場合もあります。出来る限り会社の力が分散しないように、立ち回る必要が出てきます。それが社員の為にもお客様の為にも繋がると私は考えます。