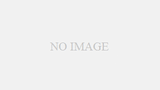役割等級制度が機能しない組織について解説します。
変化が求められる日本の人事制度
日本人一人当たりの労働生産性は近年上昇傾向にあるものの、OECD加盟国の中ではまだまだ低い状況となっています。
過去の高度成長期に掛けてメンバーシップ型と職能資格制度によって長期雇用の中、所属する企業の中で活躍するジェネラリスト人材育成していくことで、活躍できる人材を輩出してきた。会社の業績と給与も右肩上がり時代に適応していたと感じます。しかし、近年の「社会・経済環境の変化」「顧客・市場の変化」に対して「経営改革」を迫られています。生き残りをかけて様々な戦略が打ち出されている状況下において「人事戦略」をどう繋げていくかが経営者及び人事担当者による課題となっています。そこで「成果主義やジョブ型など」言葉遊びの制度変更に終わらず、社員の行動を喚起させ、生産性を向上させていく「人事制度」が求められています。
役割等級制度について
役割等級制度は経営戦略と人事戦略を結ぶ人事制度です。経営戦略に合わせた役割行動が「役割基準」として「明文化」されます。「役割基準」をもとに「要因計画、目標管理、賃金制度、人事評価」などを整えていきます。戦略の実現結果を踏まえて、そこに行きつくための「行動」と「業績責任」を明確化して「目標管理」において「測定」していきます。
役割等級制度は「戦略→役割(難易度の振り分け)→人材配置」の順に行われます。外部環境の目まぐるしく変わる環境下において、速やかに経営戦略を実行していくことは企業にとっても課題になります。社員が期待された役割を理解し行動までに落とし込む事がポイントとなります。
名ばかりの年功制になる?
役割等級制度の内容自体は良い制度だと思いますが、「設計」「運用」がポイントになります。戦略をしっかり描き、業務レベルや行動を具体化できれば、社員自身も求められているものと行動が明確になりますが、戦略があいまいだと、どの様に戦うか?(差別化)するか?その為にどのようなレベル感の業務が必要か?など描きにくきなります。人件費を抑制しようという考えから導入を検討すると、組織図を描いた時点で「誰が、何処に?」と頭によぎり、現状から減るポストに対して誰が外れるのか?など、幹部社員ですら自分自身の明日が気になります。結果、現在のポストについている人を降格若しくは役割変更できないところから、必要のない「組織や役職」が生まれるケースがあります。この様なことになると、今まで通りの「職能資格制度」「年功制」などを運用していた方が会社の中での混乱は少ないと思います。
役職の多い組織はポストが少ない組織になる
名称上のみで決裁権があるかはさておき、部長や課長でも部下がいない組織もあります。そのような場合はその人に合わせた「役職」がついていると考えられます。役割等級制度では、まずは組織骨格の見直しから始まり、ミニマムで業務が回る事を想定していきます。そうすると、なんとなくその人がいるからやっている仕事は「廃止」されることになりますので、ポストを失う可能性が出てきます。ポストを失った人に対して「新規事業」など新しい事業を始めるなどで、ポストが出来る場合は良いのですが、現状の事業部のみでポストが少なく運用する場合になると、モチベーションダウンや公平性の担保をどうするか?など対応策も合わせて検討する必要が出てきます。(特に年齢の高い役職層の抵抗になると根拠立てて話しているようで、保身しているケースが多い為、社長の断行する覚悟も必要になります。)たまに見かけますが、本部の中に部が一つ、部の中に課が一つという組織があります。この様な組織も役割等級制度で改めて「組織の役割」「成果の明文化」をしてみることで、役職の整理はできます。
変化を望まない組織
どの企業においても変化を受け入れないという話を人事の方や経営層の方から話をお伺いします。人本来の防衛本能もありますが、よほどの危険を感じない限り変化しにくいと感じます。また、日本型雇用ではよほどの事が無い限り解雇されることはありませんので、「会社におんぶにだっこ」という人も多く存在します。今までの職能資格制度や年功制で運用してきたところに制度だけ、変えても仕事(行動内容)が明文化されてなければ、結局は変わりません。今までのやってきたことから企業として変わることが明確になっている場合は社員への行動変容としても役割等級制度を取り入れるのは良いかもしれません。(自主性、自発性を求めるだけでは行動変容に繋がらないため、仕組み化が必要になります)
まとめ
役割等級制度は、経営環境の変化が激しい時代にあり、経営戦略と人事戦略を繋ぐ制度です。しかし、「戦略の明確化」「制度設計」と「制度運用」を誤ると結局は年功制のような形になります。特に「行動に繋がる、役割記載」が作成できるかで社員を動かせるカギになるます。また、役割を意識しすぎる事で「セクショナリズム」が発生するデメリットに対しては「情意評価」「クレド」など別のもので効果測定できるもので補填する仕組みが必要になります。
参考
人事制度の導入や変更を考える上で、複雑化することは避けたいです。また、100人いたら100人が満足するような制度を作ることも不可能だと思います。多少のブラックボックスがある方が、最後はその部分を言い訳に出来るので意識的に残した方がいいかも含めて検討してください。働く人が圧倒的に営業職が多く、同じ取り組みをする場合など、営業評価のみで、昇進昇格など無理に作る必要が無い場合もあります。その場合は社長と社員の文鎮型組織が機能します。それぞれの会社に合わせて、何処に進んでいきたいか?(経営方針や経営戦略)どのような行動をしていくのか?(市場や顧客にどのようにアプローチしていく事で選ばれるのか?)など決めたうえで、今の何処に「問題」があるのか?組織や制度を変えることで「どのくらいギャップを埋める事が出来るか?」定量化できないにしても仮説を持ち進める事と上手く行かないときに、どの様な軌道修正をするかも見据えておきましょう。