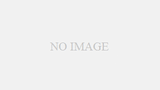・キャリコン資格取得して活用に悩んでいる方
・営業経験があり、新たな資格にチャレンジされる方
・キャリアコンサルタントを採用予定の人事の方
の参考になれば幸いです。
まずは営業スタイルの確認を行う
営業職の経験がある方がキャリアコンサルタントを目指す場合に、まず確認しておかなければならないのが、「自らの営業スタイル」です。ここで言う「自らの営業スタイル」とは業種により行う「ソリューション営業」や「インサイドセールス」というものではなく、自分自身が営業成果を上げる為の流れを指します。自らの営業スタイルでどの様に成果が上がっているかを振り返る事で「ゴールまでのプロセスを分析していく事です」何故、成果が上がっているのか感覚的な方もいらっしゃると思います。その場合はお客様の声をまとめて、何故私や会社、商品を選んで頂いているのか?を確認する中で自らの成功プロセスが眠っている場合もあります。例を上げると、商品やサービスをお客様に気に入ってもらっている人は「説明が得意」コミュニケーションを重視して人柄を気に入ってもらう事で「〇〇さんの勧めるものなら安心・・・」という「人間実がある方」相手の悩みや話を引き出すのが得意で「沢山話を聞いてくれた事で満足感を高める「質問と傾聴が得意な方」悩みや課題を確認して提案により解決を図るのが得意な「課題解決が得意な方」など一つの手法だけを使っているわけではないと思いますが、自分自身が成果を出しているケースがどの様なパターンになっているかを確認しておきましょう。
キャリアコンサルタント資格取得を目指す場合の注意点
営業職の方がキャリアコンサルタントを目指す場合に注意することは①こちらが主体となって話をしてしまう。商品を提案したり、販売する営業職の方はついついこちらから話をして自分自身のエピソードを語ってしまします。キャリアコンサルタントの資格取得を目指す上で、クライアント(相談者)が主人公ですので、悩みを言われたときに「共感」は必要ですが「自らのエピソード」を話して自らを話のメインに話すことは気を付けなければなりません。また、課題解決への「提案」に対しても「悩んでいることに対して、解決策に気づき、行動を起こしていくのはクライアント」になります。相手の悩みに対して明確に答えて、提案していく「コンサルティング営業」の方は自らの提案を出すタイミングを見定めなければ、相談者の自律的な解決までの支援にはなりません。
資格取得後のキャリアコンサルタントの活かし方
資格を取得したからと言ってすぐに仕事がある訳ではありません。
厚労省では「職業能力開発推進法、第11条、第12条において、事業主は雇用する労働者の職業能力の開発・向上が段階的かつ体系的に行われることを促進する為、「事業内職業能力開発計画」を作成するとともに、その実施に関する業務を行う「職業能力開発推進者」を選任するように努めるとされています。(努力義務)
また、平成30年7月の職業能力推進層施行規則等の改正によって、職業能力開発推進者を「キャリアコンサルタント等の職業能力開発推進者の業務を担当するための必要な能力を有する者」から選任するものと規定されました(施行期日:平成31年4月1日)出典———————————–厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000369235.pdf
条文によるとキャリアコンサルタントの活用とされていますし、「人材開発支援助成金」の利用するための要件となっています。実情は企業規模にもよりますが20%前後といった形で中々進んでいない状況です。どの企業においても人材育成の大切さは分かってはいるものの「短期的な業績確保」に追われてるという所が現状で「個人のキャリア開発を推進すること=業績の向上」までが遠く感じているのかもしれません。企業の中で人事担当者がキャリアコンサルタントの資格を取得して「職業能力開発推進者」になっているケースも多く、新規の採用は「就職支援の相談業務」が多く「経験者」が優遇されていることから「ゼロイチ」で資格取得後に活用するとなると「資格取得者の支援」や「個人のキャリア面談」で活用している方々がいらっしゃいます。資格を取得した後に5年間以内に研修を受ける必要もあるため、資格保持にも費用が掛かるため、活用イメージを具体化しておくことも大切です。
ただ、資格取得を通じて自分自身の事を理解することにも繋がりますので、「セルフマネジメント」のスキルを身に着ける事や「人脈を広げたい」という方は別の活用があります。
企業内にキャリアコンサルタントを設置するなら元営業職がオススメ
企業内にキャリアコンサルタントを設置する場合の人選ですが、人事担当者を兼任する場合があります。人事の担当者が兼任で行う場合にネックになるのが、人事異動の対象にしないことや個人情報の保護が必要になります。人事組織として個人の情報を共有することは仕事の上で必要になりますが、キャリアコンサルタントとして情報を取得した場合に人事との情報共有は本人の確認を行ってからが望ましいです。人事に情報が渡ると人材とのての良い方に働けばいいですが、それが、人事異動やネガティブ相談を受けてマイナス評価になってしまうと「相談が発生しなくなります」できれば人事組織とは別の単独した立ち位置で接する立場に「気軽に話せて、守秘が保たれる」が理想です。最後に営業職経験者を勧める理由として、ただキャリアコンサルタントを設置するだけで相談業務がいきなり発生することは少ない為、まずは積極的に自ら行動していく事が求められます。社員に対しての全体的な啓蒙活動以外にも個人への声かけなど行い、相談業務の認知を高めていく事で、相談業務が発生してくるようになります。
参考:企業内キャリアコンサルタント人選ポイント
①威圧感を与えない。人は見た目が9割という話があるように、初対面であった時に「顔つき、仕草、目つき、話し方など」から情報が圧倒的に多く、「話の内容」は心理的安全性が保たれ、信頼関係が形成されてから内容が入ってきます。人選ができるなら、直感的(本能)に緊張感を与えない人をお薦めします。
②問題解決力、ロジカルコミュニケーションのスキルがある方。「傾聴による共感」というのが基本的なスキルとしてキャリアコンサルタントに求められます。相手の立場に立ち相手が見ている悩みや課題を同じ目線で見る事で共感が得られ、信頼関係が形成されていきます。カウンセリングの場合はここで終わり相手の気持ちが楽になったという事でもいいのですが、特に企業内キャリアコンサルタントになると、相手への行動支援が求められます。信頼関係が形成された後にキャリアコンサルト側が感じる矛盾や疑問などを投げかけ、気づきを引き出すとともに、問題がある場合は「個人、組織、会社」のどこにアプローチをする事が解決に繋がるかを見極めて提案していく事が求められます。
③業界知識と市場動向の把握が出来ている方。企業内の仕事を理解していることで早期に相談者と信頼関係が気づけますし、悩みを理解することも出来ます。(適切な質問や会話が行いやすい為)また、離職の相談などを受けるケースもあります。その場合に退職後にどのような仕事をするかによって予め情報を提供することにより不必要な退職を減らすことも出来ます。(同じ業界に行く場合は特に同じ悩みにあたる事もあるため事前に解決できる手段を一緒に探して行く事ができます)
④公平性と客観性を備えている方。相談者のプライバシーや秘密を守る事は必須です。その上で公平性を客観的な目線で持ち対応していく必要があります。感情移入しすぎてしまう方は客観性が欠けてしまい本人の為と思い込みおせっかいが行き過ぎてしまうと、プライバシーも保てない事もありますし、組織や会社とのバランスを崩してしまい批判的な行動になる可能性があります。